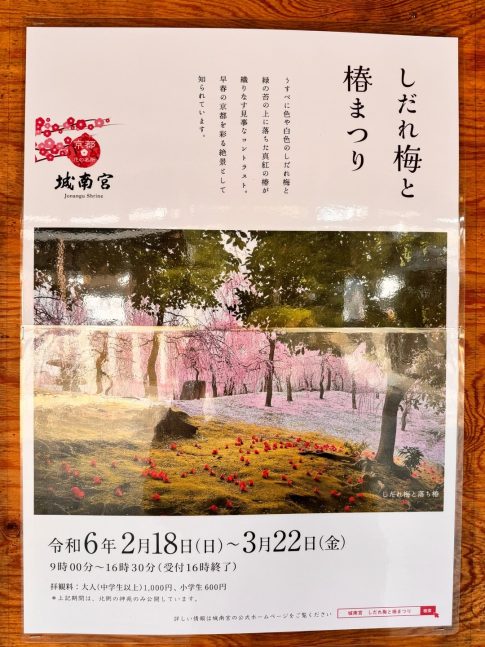今日、京都は、観測史上で最も早い梅雨入りとなりました。
平年(6月6日頃)より21日早く、昨年(6月10日頃)より25日早かったそうです。
初春から、季節は約2週間ほど、早く進んでいる感じで、菜の花も桜も例年になく早い見頃となりましたが、統計上では、梅雨はさらに早いということのようです。
昔は、生き物や植物、月やお日様をみて、季節を感じたりされたそうですが、気象庁のサイトをみると、これらの統計が管理されています。
気象庁は、生物の観測を全国的に統一された観測基準で行われるようになったのは1953年からで、すでに70年近い観測記録が各地で積み重ねられてきましたが、この生物季節観測が、2021年からは、動物の観測はすべて廃止され、植物は「うめ(開花)」「さくら(開花・満開)」「あじさい(開花)」「すすき(開花=穂が一定以上出ること)」「いちょう(黄葉・落葉)」「かえで(黄葉・落葉)」のみ6種目9現象に大幅縮小されることが気象庁から発表されました。理由は、気候変動による生態系の変化を捉えることが難しいことと予算関係があるようです。
統計データは、継続することで、その価値があり、途切れてしまうと過去のデータまでが価値が失われてしまいます。これらの危惧のなか、気象庁と環境省と国立環境研究所の三つの公的機関が協力しながら、継続されていくそうです。
身近に季節を感じられるものが、1つでもおおくあるといいですね。